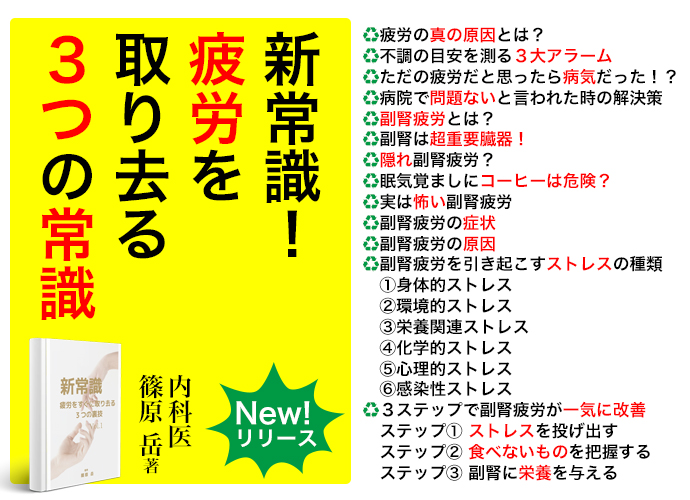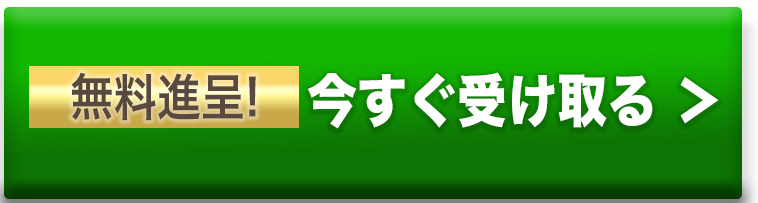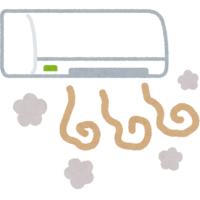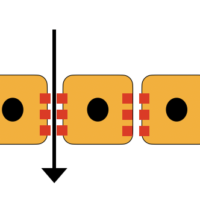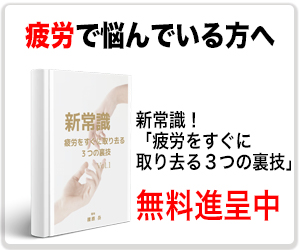最新記事 by 篠原 岳 (全て見る)
- リーキーガット診療において、東京原宿クリニックで気をつけていること - 11月 15, 2025
- 腸カンジダ診療で東京原宿クリニックが大切にしていること - 11月 15, 2025
- 朝のだるさ、日中の倦怠感。東京原宿クリニックが副腎疲労診療で大切にしていること - 11月 15, 2025
当院が「HPA軸不調」診療で最優先する「6つの柱」
「副腎疲労」という言葉は、残念ながら現在の一般医療において公式な診断名ではありません。
しかし、慢性的なストレス、睡眠不足、血糖値の乱れ、隠れた炎症、栄養不足などが複合的に絡み合い、HPA軸(視床下部–下垂体–副腎系)と呼ばれるストレス応答システムが乱れてしまうケースは非常に多く見られます。
その結果、「朝どうしても起きられない」「午前中に頭が働かない」「午後に強いだるさを感じる」「無性に塩辛いものや甘いものが欲しくなる」「立ちくらみ」「頭に霧がかかった感じ(ブレインフォグ)」といった症状が長く続く方が少なくありません。
東京原宿クリニックでは、この問題を「HPA軸のストレス不均衡」と捉え、用語上の議論に留まらず、症状の裏にある根本原因を見つけることを最優先します。
本記事では、当院が「副腎疲労(HPA軸不調)」の診療において最も大切にしている「安全性・鑑別・生活改善・検査・再現性・フォロー」という6つの柱について、当院の臨床原則に基づき体系的に解説します。東京原宿クリニックの副腎疲労治療につきましては、こちらをご参照ください。
当院の基本的な考え方:「副腎疲労」という言葉に惑わされない
当院では、まず用語と考え方を整理することから始めます。
- 副腎不全 (Adrenal Insufficiency):確立された疾患概念です。副腎がホルモン(コルチゾールなど)を十分に出せない状態で、命に関わるため、迅速かつ適切な検査・治療が必要です。
- 副腎疲労 (Adrenal Fatigue):医学的に未確立の言葉です。臨床現場では、上記のようなHPA軸のストレス応答が機能的に乱れた状態を指す、便宜的なラベルとして使われることがあります。
当院の方針は、この「ラベル」の是非を問うことではありません。私たちが優先するのは、症状の背景にある要因(ストレス、睡眠、血糖、炎症、栄養)を丁寧に分解し、①危険な疾患(副腎不全など)を確実に見逃さず、②生活・栄養・生体リズムの再建をサポートすることです。

東京原宿クリニックが「HPA軸不調」診療で大切にする6つの柱
当院が臨床現場でとくに注意している原則を、6つの柱に分けて解説します。
【柱1:安全性と鑑別の徹底】(最優先事項)
症状の背景に「命に関わる病気」や「医療的なリスク」が隠れていないかを見極めることが、全ての土台となります。
- レッドフラッグ(危険信号)の迅速な鑑別副腎不全、長期ステロイド薬の急な中断、重度の電解質異常(低ナトリウム血症など)、著しい低血圧や体重減少など、緊急対応が必要な病態を最優先で除外します。
- 鑑別の幅を意図的に広く持つ「副腎疲労」様の症状を引き起こす他の原因は多数あります。甲状腺機能異常、鉄欠乏、ビタミンB12欠乏、睡眠時無呼吸症候群、うつ・不安障害、POTS(体位性頻脈症候群)、慢性炎症(慢性副鼻腔炎や上咽頭炎など)、薬剤の影響(ベンゾジアゼピン系薬剤、カフェイン過多)などを常に念頭に置き、同時に精査します。
- サプリメントの安全性を厳守自己判断でのサプリメント使用は、時にリスクを伴います。
- 甘草(グリチルリチン):偽アルドステロン症(高血圧、低カリウム血症、不整脈)のリスクがあり、特に高齢者や利尿薬服用者は注意が必要です。
- アシュワガンダ:まれに甲状腺機能亢進や無痛性甲状腺炎の報告があり、甲状腺疾患の既往がある方は慎重であるべきです。
- 海外の「アドレナルサポート」製品:一部の製品で、ステロイドや甲状腺ホルモン成分の混入が分析・報告されています。FDA(米国食品医薬品局)からも未表示の合成ステロイド混入について度々警告が出ており、品質の信頼できない製品の連用は非常に危険です。
【柱2:生活改善の具体化】(治療の土台)
HPA軸の不調は「生活習慣の乱れ」そのものが原因、あるいは増悪因子となっていることが大半です。
- 睡眠の質を最重要KPI(目標)に
HPA軸の機能は「概日リズム(サーカディアンリズム)」と直結しています。当院では「起床時刻の固定」を最優先とし、起床後の朝日光暴露、夜間の強光・ブルーライト回避、就寝前のルーティン(温冷・呼吸法)などをセットで指導し、睡眠の質を高めます。 - 食事・血糖・電解質の微調整
血糖値の乱高下はHPA軸に大きな負担をかけます。特に「朝食」を重視し、たんぱく質・脂質・食物繊維を含む食事で血糖の安定化を図ります。また、低血圧や立ちくらみが強い場合はナトリウム(塩分)摂取の調整も検討します(※高血圧・腎疾患等がある場合は主治医判断)。 - 腸・炎症・ヒスタミンの同時管理
SIBO/SIFO(腸内細菌・真菌の異常増殖)、リーキーガット、食物アレルギー・過敏症、慢性上咽頭炎などの「慢性的な炎症」は、持続的にHPA軸に負荷をかけます。必要に応じて腸内関連検査や食事の再設計を並行して行います。

【柱3:検査(唾液コルチゾール)の再現性】(客観的な評価)
HPA軸の状態を評価するため、当院は唾液コルチゾール(多点時系列)とDHEA-sの検査を検討します。特に唾液コルチゾール検査は、その「やり方」で結果が大きく変わってしまいます。
- CAR (コルチゾール覚醒反応) を重視
コルチゾールは、起床直後から30~45分で一時的に急上昇します。これをCAR (Cortisol Awakening Response)と呼び、HPA軸の健常性を示す重要な指標です。この「朝の立ち上がり」が鈍い場合、起床困難や午前中の不調に直結します。 - 検査条件の「標準化」を徹底
CARや日内リズムを正確に評価するため、当院では検査キット(自宅採取)の実施方法を指導します。- 採取タイミングの厳守(例:起床直後、起床30分後、昼、就寝前)、採取条件の統一(前日の就寝時刻、カフェイン・運動の制限、当日の起床直後の行動など)
これらを守らなければ、検査結果の信頼性が著しく低下するため、当院は「再現性」を最も重視して検査設計を行います。
- 採取タイミングの厳守(例:起床直後、起床30分後、昼、就寝前)、採取条件の統一(前日の就寝時刻、カフェイン・運動の制限、当日の起床直後の行動など)
【柱4:介入の優先順位付け】
睡眠、食事、栄養素、ストレス管理、腸内環境…すべてが重要ですが、同時に全てを行うのは困難です。検査結果と生活歴に基づき、「今、最も改善インパクトが大きいのはどこか」を見極め、介入の優先順位をつけます。
- 睡眠・光・行動(起床固定、朝の光、夜のライトダウン)
- 食事・血糖(朝食のたんぱく質、間食の質)
- 栄養素(検査に基づき、C/B群/Mg/Znなどを個別化)
- 腸内・炎症(SIBOや食物反応があれば先に制御)
- ストレス・情動(呼吸法、瞑想、軽運動)
【柱5:丁寧なフォローアップとモニタリング】
改善は一直線ではありません。客観的な指標と主観的な体感を両輪で追いかけます。
- 二軸でのモニタリング
「起床時の眠気」「午前中の活動量」「夕方のだるさ」などの主観KPIと、睡眠時間などの客観KPIを伺い、3~6ヶ月単位での「傾向線」を確認します。 - 検査のタイミング検査は「方針変更が必要な時」や「症状が踊り場に来た時」に実施します。過剰検査も過少検査も避け、臨床判断に基づいて適宜再評価を行います。
【柱6:現実的な期待値の調整】(改善は“マラソン”)
栄養療法は、体質改善の側面が強いアプローチです。
「このサプリを飲めば明日治る」といった魔法ではありません。3~6ヶ月かけて生活習慣という「土台」を整え、安定するまでには1~2年を目安に伴走するケースもあります(個人差あり)。当院では、この現実的な見通しを共有することを大切にしています。
当院での診療の流れ(初診から改善まで)
当院の栄養外来は完全予約制です。
- ご予約:栄養外来よりご予約ください。
- 初診:医師による診察(30分)を行います。必要に応じ、栄養士による説明を追加します。
- 検査:ご自宅で実施いただく検査キット(唾液、尿、便など)や、院内での採血を組み合わせて実施します。
- 結果説明・方針決定:検査結果判明以降に再度ご来院いただき、解析レポートを用いて現状を分析し、治療の優先順位を決定します。
※自費診療である栄養外来の費用・進め方に不安がある場合は、まず「総合カウンセリング」をご利用いただくことも可能です。
4. よくあるご質問(FAQ)
Q1. 「副腎疲労」は病名ですか?
A. 現時点で医学的に確立した診断名ではありません。ただし、症状を引き起こすHPA軸の機能的な乱れは存在すると考えられます。当院では用語にこだわらず、危険な疾患(副腎不全など)を除外し、機能的な課題の是正に集中します。
Q2. 唾液コルチゾール検査は信頼できますか?
A. 採取タイミングや条件の「標準化」を厳守すれば、CAR(覚醒時反応)や日内リズムの評価に非常に有用です。当院ではこの「標準化」を徹底しています。
Q3. どれくらいで良くなりますか?
A. 体質や背景要因により個人差が非常に大きいですが、一般的に3~6ヶ月で生活の土台を調整し、1~2年かけて定着を目指す、というのが目安です。
Q4. サプリは何から始めるべきですか?
A. 当院は「安全性→適応→期間」の順で評価します。自己判断での甘草・アシュワガンダ・動物性腺製品の長期使用はリスクを伴うため推奨しません。まずは検査結果に基づき、ビタミンC、B群、マグネシウム、亜鉛などの基本的な栄養素の調整から始めます。
5. まとめ
東京原宿クリニックが「副腎疲労(HPA軸機能不全)」の診療で大切にしているのは、言葉に振り回されず、以下の原則を守ることです。
- レッドフラッグ優先:副腎不全など、危険な疾患の除外を最優先する。
- HPA軸の「機能」に着目:睡眠・炎症・血糖・栄養・心理の相互作用を分解する。
- 検査は再現性重視:特にCAR(コルチゾール覚醒反応)の評価と、検査条件の標準化を徹底する。
- サプリは安全性第一:甘草・アシュワガンダ・腺製品の自己判断での使用リスクを認識し、安全な栄養素から個別化する。
- 改善は“マラソン”:3~6ヶ月の土台づくりと、1~2年での定着を目標に、現実的な目線で伴走する。
長く続く不調でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。