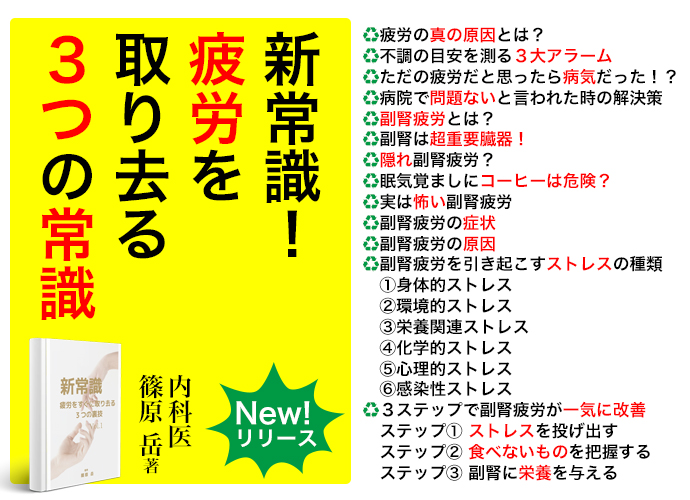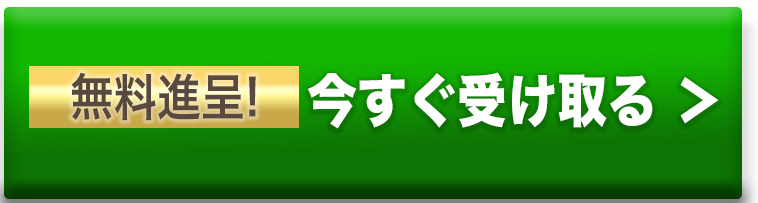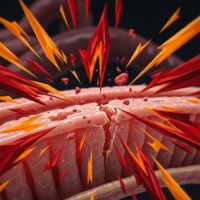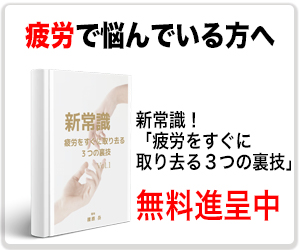最新記事 by 篠原 岳 (全て見る)
- リーキーガット診療において、東京原宿クリニックで気をつけていること - 11月 15, 2025
- 腸カンジダ診療で東京原宿クリニックが大切にしていること - 11月 15, 2025
- 朝のだるさ、日中の倦怠感。東京原宿クリニックが副腎疲労診療で大切にしていること - 11月 15, 2025
「お腹の張りがなかなか治らない」「もしかして腸カンジダかも?」とご相談いただくことが増えています。
腸カンジダ(腸管カンジダ)、または小腸に増えるSIFO(小腸真菌増殖)と呼ばれる状態は、まだ研究途上の分野でもあり、診断や治療には慎重さが求められます。
東京原宿クリニックでは、腸カンジダの診療において、過剰な診断や不十分な治療を避け、「安全性」と「再発予防」を何よりも重視しています。
この記事では、当院が腸カンジダの診療で具体的にどのような点に気をつけ、どのような方針で治療を進めているのかを、分かりやすくご説明します。
腸カンジダについての詳細は東京原宿クリニックのページで詳細しています。
「腸カンジダ/SIFO」とは? どう考えるか
腸カンジダとは、簡単に言えば「腸の中で真菌(カビの一種)が増えすぎてしまい、お腹の不調などを引き起こしている状態」を指します。
カンジダ菌自体は、健康な人の腸にも存在する常在菌です。しかし、何らかの理由でバランスが崩れて異常に増殖すると、問題を引き起こすことがあると考えられています。
ただし、「どこからが異常な増殖か」「症状とどう関係しているか」については、まだ医学的に明確な基準が定まっていない部分も多く、診断には総合的な判断が必要です。
SIFOは、特に小腸でカンジダが増えて症状が出ていることを示します。SIFOにつきましては、東京原宿クリニックのSIFOのページをご参照ください。
当院が「腸カンジダ」を疑うとき
当院では、やみくもに腸カンジダと診断するのではなく、以下のような場合に可能性を考慮します。
- お腹の張りがなかなか改善しない場合
- 「SIBO(小腸内細菌増殖症)」の治療(抗菌薬など)を行っても、ガスの発生や膨満感がスッキリしない、または再発を繰り返す場合。細菌は減っても、真菌が残っている(あるいは優位になっている)可能性を考えます。SIBOにつきましては、東京原宿クリニックのページをご参照ください。
- 繰り返すカンジダ症状とお腹の不調がある場合
- 口の中や皮膚、膣などのカンジダ症を繰り返しており、同時にお腹の張りや吐き気などが続いている場合。

診断と検査の「現実」:できること・できないこと
「腸カンジダかどうか、検査でハッキリさせたい」と思われるかもしれませんが、診断はそう単純ではありません。
- 最も確実とされる検査(小腸液の培養)
- 内視鏡を使って小腸の液を直接採取し培養する方法が、現時点では最も確実とされます。しかし、体への負担が大きく、汚染のリスクや実施できる施設が限られるため、一般的ではありません。
- 便検査や尿検査(有機酸検査)で分かること
- 便検査でカンジダ菌が見つかっても、それだけでは「腸カンジダ」の確定診断にはなりません。なぜなら、カンジダはもともと腸にいる常在菌であり、便の検査だけでは「腸で異常増殖しているか」までは判断できないからです。
- 尿中の有機酸(アラビノースなど)を調べる検査も、あくまで「間接的な指標」の一つです。
- 当院では、これらの検査結果を参考情報として位置づけ、症状や病歴、他の検査結果と合わせて総合的に判断します。
- 呼気検査(息の検査)は?
- これはSIBO(細菌の増殖)を調べる検査であり、真菌(カビ)の増殖を直接調べることはできません。
当院の治療方針:安全で、持続可能な方法を
当院の治療は、「薬物治療」と「食事・生活の土台づくり」を両輪で進めます。
抗真菌薬(飲み薬)の考え方と安全管理
腸カンジダが強く疑われ、症状の改善が見込めると判断した場合、抗真菌薬(カビを抑える薬)を短期間使用することがあります。
ただし、薬である以上、安全性には細心の注意を払います。
- 安全性のチェックを徹底
- 抗真菌薬の中には、まれに肝機能に影響を与えたり、他の薬との飲み合わせ(相互作用)が問題になったりするものがあります。
- 特に血液をサラサラにする薬(ワルファリン)や、特定の薬(CYP3A4という酵素で代謝される薬)との併用には注意が必要です。
- 当院では、治療開始前に必ず血液検査(肝機能など)を行い、現在服用中のお薬をすべて確認した上で、安全に治療を進めます。
- 副作用やダイオフなどが起きていないかどうかを慎重にみていきます。

食事と栄養:「極端」でなく「持続可能」に
腸カンジダというと、「カンジダ・クレンズ」のような極端な食事制限(糖質を徹底的に排除するなど)をイメージされるかもしれません。
当院では、こうした極端な食事療法は推奨していません。
有効性が科学的に確立されていないだけでなく、栄養不良や心理的なストレスを招き、長続きしない可能性が高いためです。
当院が目指すのは、「持続可能な食生活」です。
- 精製された糖質(お菓子、ジュース、白いパンなど)の摂りすぎを減らす。
- 腸内環境全体を整えるため、食物繊維や良質なタンパク質、ビタミン、ミネラルなど、栄養の密度を上げる。
- 超加工食品(スナック菓子、インスタント食品など)を減らし、バランスの取れた食事を心がける。
※SIBO(細菌)の症状が強い場合は、一時的に「低FODMAP食」を試すこともありますが、これも短期間で再導入(食べられるものを増やす)ことを基本とします。
プロバイオティクス(善玉菌)など
特定の善玉菌(プロバイオティクス)や酵母菌(サッカロマイセス・ブラウディ)がカンジダの付着を抑える可能性も研究されていますが、まだ腸カンジダ/SIFO患者さんでの大規模な証拠は十分ではありません。
当院では「まず試してみて、ご自身の体調に合うか反応を見る」というスタンスで、慎重に使用を検討します。
(※免疫力が極端に低下している方など、使用に注意が必要なケースもあります。)
再発予防の鍵は「腸のバリア機能」
腸カンジダやSIFOは、腸のバリア機能の低下(いわゆる「リーキーガット」)と深く関連していると考えられます。
薬で一時的に真菌を抑えても、腸の環境という「土台」が整っていなければ、再発しやすくなります。
- 十分な睡眠
- ストレスの管理
- 自律神経のバランス
- 口腔内の衛生管理(歯周病など)
- 適切な栄養(脂質、食物繊維、微量栄養素)
当院では、薬物治療と並行して、こうした生活の土台を見直すことを非常に重視しています。腸のバリア機能を回復させることが、根本的な再発予防につながると考えているからです。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 腸カンジダは検査で確定できますか?
A. 残念ながら「これさえ受ければ100%確定」という簡単な検査はありません。最も確実とされる小腸の液を採る検査は体への負担が大きく、一般的ではありません。便や尿の検査はあくまで間接的な情報と捉え、症状や病歴、治療への反応を総合して判断します。
Q2. どのくらいで良くなりますか?再発は?
A. 個人差が非常に大きいです。抗真菌薬で8週間で症状が和らぐ方もいますが、薬だけで「根絶」できるという証拠はまだ限定的です。再発を防ぐためには、食事、睡眠、ストレス管理といった「生活の土台」を整えることが不可欠です。
Q3. “カンジダ・クレンズ”は有効ですか?
A. その有効性を示す質の高い医学研究は、現時点では不足しています。当院では、極端な食事制限は栄養の偏りやストレスを招くリスクがあるため推奨しておらず、持続可能な栄養設計を優先します。
Q4. 抗真菌薬は安全ですか?
A. 概ね安全に使用できる薬ですが、まれな肝障害や、他の薬との飲み合わせ(相互作用)には注意が必要です。当院では、安全に使用できるかを事前にしっかり確認し、治療中も血液検査などでモニタリングを徹底します。
まとめ:当院のスタンス
- 腸カンジダ/SIFOは、まだ研究途上の分野であり、総合的な診断を原則とします。
- 「SIBO治療で治らない」など、臨床経過から丁寧に可能性を探ります。
- 便や尿の検査は間接情報として扱い、それだけで診断を確定しません。
- 治療は「安全第一」。抗真菌薬は安全管理(肝機能・飲み合わせ)を徹底した上で短期使用を検討します。
- 極端な食事制限(クレンズ)は推奨しません。栄養バランスの取れた「持続可能」な食生活の土台づくりを重視します。
- 再発予防のため、腸のバリア機能(リーキーガット)を整える生活支援を継続します。
お腹の不調が続き、不安に思われている方は、ぜひ一度ご相談ください。